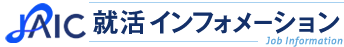- 「自動車業界での就職活動がうまくいかない」
- 「自動車業界に就職したいけれど、どの職種が自分に合っているのか分からない」
自分に合った仕事を見つけたいけれど、自動車業界のトレンドや必要なスキルがよく分からない就活生は多いですよね。
また、業界特有の選考基準や求められるスキルが不安で、どこから手をつければ良いのか迷っている方もいるかもしれません。
そんな就活生におすすめなのが、自分に合った職種を見つけるための業界研究と、選考突破するための準備法です。
今回の記事では、自動車業界での就職活動のコツや、業界内で求められるスキルについてご紹介します。
日本のリーディングカンパニー自動車業界とは?
自動車業界とは、自動車や自動車に必要な部品の開発や生産などを行う業者を指します。自動車業界は国内の市場規模を年々拡大している、いわば日本経済を支える重要な産業です。
一般社団法人日本自動車工業会が発表する「日本の自動車工業2024」によると、2022年の日本国内の自動車製造業の製造出荷額等は約63兆円でした。
これは前年の11%増の額であり、国内の全製造業の製造出荷額等の約17%を自動車製造業が占める結果となりました。
自動車関連産業は自動車の関連資材の調達や製造をはじめ、整備・販売など様々な分野を含みます。広範囲に渡る自動車業界の就業人口は558万人と日本の全就業人口の約8%を占めています。
日本の経済を支える重要産業である自動車業界ですが近年変動期を迎えており、従来とは異なる事業展開が求められると共に採用人材にも変化が生じつつあります。
自動車業界の仕事内容は?
自動車業界と一括りに言っても、仕事内容は多岐に渡ります。ここでは自動車業界に該当する主な仕事内容を3つ紹介します。
- 企画
- 研究開発
- 生産
企画
自動車業界の企画職は、市場調査をはじめ、コンセプトの立案、商品企画や販売のプロモーションなどを行います。自社製品の売上向上のために様々な施策を立案する重要な役割を担っています。
どのような自動車が求められているのか消費者のニーズ調査を行い、どのような商品を製造するかを企画します。
どういった販売方法がより販売促進に繋がるかも調査し、販売方法の立案も行います。
研究開発
自動車業界における研究開発職は新しい技術や製品の開発、改良、試験などを行う職種です。
研究開発職と一括りに言ってもいくつかの分野から構成されており、車両開発やエンジンやモーターなどの開発、自動運転などの運転支援システムの開発などがあります。
専門的な知識や技術を必要とする職種の為、機械工学や情報工学などを先行した理系出身者が多く採用される傾向があります。
自動車業界の研究開発職は自動車の新しい技術を生み出す上で重要な役割を担う役職です。
生産
生産職は工場での自動車や部品の製造・組み立て・品質管理などを行います。
具体的には工場のラインで自動車や部品の組み立てを行う製造オペレーターや、生産ラインをより効率的に動かすための設計や改良を行う生産技術部門、完成した車両や部品の品質をチェックし、不良品を防ぐ品質管理部門などがあります。
生産職は自動車を実際に作り上げる最前線の職種です。
技術職に該当するこの職種においては機械工学や電気・電子工学などの知識がある人が多く所属している傾向があります。
自動車業界の売上高
日本経済を大きく支える産業である自動車業界ですが、ここでは国内の自動車産業における売上高をランキング形式で紹介します。
国内メーカー売上高ランキング
2023年度の国内の自動車メーカーの売上は以下の表の様になっています。
トヨタ自動車が約45兆円の売り上げで2位の本田技研工業と2倍以上の差をつけて圧倒的な国内シェアを誇っています。
続いて、本田技研工業や三菱商事がランクインしています。
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
| 1位 | トヨタ自動車 | 45,095,325 |
| 2位 | 本田技研工業 | 20,428,802 |
| 3位 | 三菱商事 | 19,567,601 |
| 4位 | 日産自動車 | 12,685,716 |
| 5位 | スズキ | 5,374,255 |
| 6位 | マツダ | 4,827,662 |
| 7位 | SUBARU | 4,702,947 |
| 8位 | いすゞ自動車 | 3,386,676 |
| 9位 | 三菱自動車工業 | 2,789,589 |
| 10位 | 日野自動車 | 1,516,255 |
自動車業界には様々な企業があり、それぞれが異なる特徴を持っています。
例えば、トヨタ自動車は圧倒的な規模と国内外での高いブランド力を誇り、製造から販売、研究開発に至るまで多岐にわたる職種を提供しています。
ホンダや日産、スズキといった企業も同様に安定した成長を遂げており、各企業の特性を理解し、自分の適性や興味に合った企業を選ぶことが大切です。
また、自動車業界で求められるスキルは多岐にわたります。エンジニア職では、機械工学や電気工学の知識が重要です。また、最近では自動運転技術やEV(電気自動車)の開発が進んでいます。
営業職やマーケティング職に関しては、業界に対する深い理解とともに、顧客のニーズを捉える力が重要となります。
自動車業界は技術革新が進んでいる分、常に新しい知識やスキルを求められる分野でもあります。そのため、自分の専門性を磨き、常に学び続ける姿勢が重要となります。
自動車業界のビジネスモデル
国内産業の大部分を支えている自動車産業ですが、ビジネスモデルはどのようになっているのでしょうか。
ここでは自動車業界のビジネスモデルを4つの業種でそれぞれ紹介します。
- 自動車メーカー
- 部品・素材メーカー
- ディーラー
- 関連サービス会社
自動車メーカー
自動車メーカーのビジネスモデルは大きく以下の4つに分けられます。
- 新車販売での収益
- アフターサービスによる収益
- 金融サービスによる収益
- 技術ライセンス提供による収益
1つ目の新車販売は自社で新車を設計、製造、販売することで収益を得ます。
2つ目のアフターサービスは点検・整備・修理・部品交換などのサービスを提供し、顧客満足度を高めると同時に収益を上げます。
3つ目の金融サービスは自社系列の金融会社を通じて、ローンやリースなどの金融商品を提供し、金利や手数料による利益を得ています。
4つ目の技術ライセンスは自社の技術や特許を他のメーカーにライセンス供与することで販売時の手数料やマージンから収益を得ています。
このように複数の商品やサービスを組み合わせたビジネスモデルを展開して収益を得ています。
部品・素材メーカー
部品・素材メーカーはその名の通り自動車に必要な部品や素材を製造しています。部品・素材メーカーのビジネスモデルは主に受注による部品製造で収益を得ています。
1つ目の受注販売による収益は、自動車メーカーから部品製造の依頼を受けて自社で部品を開発、製造、納品することで収益を得ています。
自動車メーカーへ直接部品や素材を納品するほかに、サプライチェーンという仕組みも存在します。
自動車業界は自動車メーカーを筆頭に部品製造業者がピラミッド状に連なっており、自動車に必要な部品をいくつもの部品・素材メーカーが連鎖的に供給しています。
数万に及ぶ部品をある程度段階ごとにまとめて納品することで生産ラインに負荷がかからないように調整しており、納品後に自動車メーカーから収益が配当されるようになっています。
ディーラー
ディーラーとは主に車を販売している業者を指します。カーディーラーのビジネスモデルは大きく以下の3つに分けられます。
- 新車・中古車販売による収益
- アフターサービス提供による収益
- 金融・保険商品の販売による収益
1つ目の新車・中古車販売による収益はその名の通り、自動車メーカーから仕入れた新車や中古車を販売することで収益を得ます。
2つ目の新車・中古車販売による収益は車両の点検・整備・修理などのサービスを提供することで出た収益を指します。
3つ目の金融・保険商品の販売による収益は、自動車ローンや各種保険をセットで販売することで手数料による収益を得ます。
ディーラーは新車販売で獲得した顧客を長期的に維持し、アフターサービスを通じて継続的な収益を獲得しています。
ディーラー独自の専門知識や純正部品を活用し、一般のカーケア店よりも高い価格設定でサービスを提供する特徴があります。
関連サービス会社
自動車関連サービス会社のビジネスモデルは多岐に渡ります。自動車関連サービス会社にはカーシェアリングサービス提供会社や自動車修理会社などが該当します。
カーシェアリングサービス提供会社におけるビジネスモデルは、ライドシェアやカーシェアなどのサービス利用によって収益を得ています。
自動車修理会社では故障車や修理が必要な場合の修理サービスを提供することで収益を得ています。
関連サービス会社においては様々な会社が存在するため、このほかにも該当する企業が多くありそのビジネスモデルも異なります。
気になる自動車関連サービスを提供している会社があればご自身でリサーチしてみることをおすすめします。
自動車業界の最新動向
近年ではAIの発達や人々の暮らしの変化により、自動車業界も大きく動向が変化しています。
ここでは自動車業界の最新動向に関わる要因を4つに分けて紹介します。
- 自動運転技術の進歩
- MaaSの推進
- カーシェアリングの流行
- 国内の車離れの進行
自動運転技術の進歩
近年の自動車業界に変化を及ぼしている要因のひとつに自動運転技術の進歩が挙げられます。
自動運転とは車両がドライバーの操作なしに自律的に走行する技術のことを指します。AIやセンサー、カメラ、GPSなどの最新技術を駆使して周囲の状況を認識し、適切な判断を行いながら運転します。
自動運転技術が進歩したことで従来の自動車メーカーに加え、IT関連企業も自動運転開発事業に参入しています。
車両自体を指すハードウエアだけでなく、自動運転システムを含め、ECUやナビソフトなどに該当するソフトウェアやデータ処理能力も必要とされてきています。
MaaSの推進
MaaSとはMobility as a Serviceの略称で、様々な交通手段を一つの移動サービスとして統合し、目的地までのルート検索、予約、決済を一括して行えるサービスを指します。
MaaSの推進により、自動車メーカーは、車を製造・販売する企業から、モビリティサービスを提供する企業へと転換の必要を迫られています。
また、大手自動車メーカーがMaaS関連の新規事業を積極的に展開を始めたり、自動車メーカー以外にもIT企業が市場に参入し始めたことで競争が激化しています。
MaaSの推進により自動車業界の採用基準にも変化が起こっています。
従来は工学系の技術や知識に富んだ人材を積極的に求めていましたが、近年ではサービス設計やデータ分析など、幅広い知識を持つ人材の採用にも力が入れられています。
カーシェアリングの流行
カーシェアリングサービスの需要は近年急激に高まりを見せています。カーシェアリングサービスの流行も自動車業界へ変化を及ぼす大きな要因です。
新型コロナウイルスの流行に伴い、公共交通機関の代替手段としてカーシェアリングの利用傾向が高まりました。
他にも若年層を中心に車の購入費や維持費の高さから所有を避ける代わりにカーシェアリングを利用する割合が高まっています。
このような理由からカーシェアリング市場は大幅な成長を見せており、利用者の拡大とともに全国各地でステーションの設置が推進されています。
カーシェアリングの需要拡大によって自動車メーカーは、車の製造・販売だけでなく、モビリティサービス提供の必要を迫られています。
国内の車離れの進行
近年の車離れの進行も自動車業界に変化を及ぼす大きな要因になっています。
車離れの要因として、公共交通機関が充実している都市部の人口集中による車の必要性低下や、レンタカーやカーシェアの利用、車の購入に対する価値観の変化などが挙げられます。
車離れが進んだことで国内市場での新車販売台数が減少し、メーカーの収益にも大きな影響が出ています。
こうした傾向に対し、自動車メーカーはカーシェアリングなどの新たなモビリティサービス事業に参入することで対応を目指しています。
自動車業界の就職に向いている人
ここでは自動車業界の就職に向いている人の特徴を3つ紹介します。
以下で紹介する特徴は自動車業界での就職に有利に働く場合が多いので、自身と照らし合わせた際に重なる部分があれば自己PRに盛り込むのもおすすめです。
- チームワークを大切にできる人
- グローバルな視点を持っている人
- ものづくりが好きな人
チームワークを大切にできる人
自動車業界の就職に向いている人の特徴の一つにチームワークを大切にできる人が挙げられます。
自動車業界では多くの部門や技術者が連携して業務を進めることが多いです。
チームワークを大切にできる人は、チームプロジェクトの円滑な進行や部門間の情報共有といった様々な場面で重宝されます。
グローバルな視点を持っている人
自動車業界の就職ではグローバルな視点を持っている人も重宝されます。
近年自動車業界は国際的な展開が進んでおり、海外との取引や協力が不可欠です。
海外の取引先や技術者とのコミュニケーションはもちろん、海外赴任や国際プロジェクトへの参加機会にも重宝されます。
自動車業界への就職を検討しているのならば、海外の自動車業界の動向に目を向けておくのも良いでしょう。
ものづくりが好きな人
自動車業界の就職に向いている人の特徴にものづくりが好きな人も当てはまります。
自動車業界は製造業の中核であり、製品開発や生産に深く関わります。
ものづくりが好きであることで高品質な自動車の製造に繋げたり、長期的なプロジェクトでも熱意を持って取り組めることが期待されるため就職時には重宝されます。
自動車業界に就職するための準備・対策
ここでは自動車業界に就職するための準備や対策を3つ紹介します。自動車業界への就職を目指している方は必見の内容です。
ぜひここで紹介する内容を参考にご自身の就職活動に生かしてください。
- エントリーシートの志望動機に力を入れる
- 自動車業界で評価される
- 自己PRを書く
- 自動車業界の選考プロセスを理解する
エントリーシートの志望動機に力を入れる
エントリーシート(ES)は応募者の基本情報の他、志望動機や自己PRといった自身の魅力や企業への熱意を示すための重要なツールです。
業務適性や企業の社風・ビジョンとのマッチング、貢献可能性の判断に活用されます。
ESは面接の参考資料として使用されます。場合によってはESの内容で合否が出されることもあります。いわば、企業が最初に学生を見極めるための資料です。
志望動機では競合他社の比較を徹底し、なぜその会社に入りたいのかを伝えましょう。
志望する会社の理念や特徴を十分に研究し、競合他社と比較した上でなぜその会社を選んだのかを明確に説明しましょう。
自動車業界で評価される自己PRを書く
自動車業界で評価される自己PRを用意することで有利に就職活動を進められます。
自動車業界の就職で評価されやすいポイントとして、先ほど紹介した就職に向いている人の特徴を盛り込むこともひとつの有効な手段です。
その他、自動車業界特有の専門技術や知識がある場合は学歴や経歴・取得資格欄だけでなく具体的なエピソードを交えつつ記述しましょう。
自動車業界の選考プロセスを理解する
自動車業界への就職を有利に進めるうえで自動車業界の選考プロセスを理解することは重要です。
選考開始の時期や進行手順を事前に把握し、準備期間が短くなってしまったり申し込みを逃したりすることの無いようにしましょう。
自動車業界に該当する製造業ではおおむね3月頃に本選考が始まり、6月に内定を出すのが一般的なスケジュールになっています。
大手になるとエントリーシートによる一次選考後、二次選考、三次選考にまで及ぶ選考プロセスを経て本採用に至るケースが多いです。
自動車業界では技術職採用の枠が最も多く、事務職や業務職での採用枠の方が少ない傾向にあります。それによりエントリーの回数も企業によっては異なる場合があるので、事前に選考スケジュールを把握して間違いのないようにしておきましょう。
まとめ
本記事では、自動車業界での就職活動のコツや、業界内で求められるスキルについてご紹介しました。
自動車業界は国内で大きな市場を占める業界であり、日々様々な発展を遂げています。自動車業界への就職を目指している方は、頻繁に自動車業界の動向を確認しておくことをおすすめします。
自動車業界へ就職したい方は、ぜひ本記事の内容をご自身の就職活動に活かしてください。